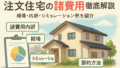「家族全員で相続放棄したら、その後の借金や不動産管理はいったいどうなるの?」
こう悩まれる方は決して少なくありません。日本では毎年【20万件以上】の相続放棄手続きが家庭裁判所に申立てられています。しかも、複数の相続人全員で放棄した場合、相続財産は「次順位」や「国庫」へと移行し、不動産や借金の処理、管理義務の分担にも注意が必要です。
「想定外の管理費や債権者から突然連絡が…」「きちんと放棄できたはずなのに家の処分で困っている」といったご相談も多く、放棄後の手続きや負担分担でトラブルが続出しています。
実は、管理人の選任費用や必要書類の不備など、細かなミスで申述が却下されるケースも散見されます。放棄で損失や想定外の負担を回避するには、正確な最新知識と実務の流れをおさえることが不可欠です。
本記事では、相続放棄を全員で確実かつ効率良く進めるために、【法的な仕組み】と【実務上の注意点】を豊富な実例・数値を交えて網羅的に解説。ぜひ最後までご覧いただき、ご自身のケースに役立ててください。
相続放棄を全員で行う前に押さえるべき基本知識と選択のリスク
相続放棄の法的な意味と成立条件―全員での放棄成立に必要な要件と期限を具体的に解説
相続放棄は相続財産の一切を受け取らない意思を家庭裁判所に申述して認めてもらう法的手続きです。相続人全員が放棄した場合、次順位の相続人に権利が移りますが、全ての相続順位が放棄した場合には相続人不存在となり、相続財産管理人の選任が必要になります。
全員で相続放棄する場合でも、それぞれが家庭裁判所に個別に申述しなければ成立しません。期限は「被相続人の死亡を知った日から3か月以内」とされています。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものと見なされ、放棄できなくなります。
主な手続きの流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 必要書類の準備 | 戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、申述書など |
| 家庭裁判所への申述 | 相続人ごとに申述 |
| 裁判所の審査 | 書類や意思確認後、「受理証明書」の発行 |
| 次順位の相続人へ通知 | 全員放棄が認められると、次順位に権利が移行 |
ポイントは「全員で同時に放棄を進める意識」「期限厳守」「書類不備を避けること」です。
放棄が認められないパターンの詳細解説―手続き不備や無効リスクの注意点
相続放棄は申述の内容やタイミングに不備があると認められません。特に注意したいのは以下の点です。
-
期限を過ぎて申述した場合
-
放棄後に遺産を処分した、または現に財産を使った場合
-
空欄や記載ミス等、申述書類の不備
-
既に遺産分割協議を行った場合
また、全員で放棄した場合でも、次順位の法定相続人(例えば兄弟姉妹や甥姪)が自動的に相続権を取得します。全ての順位の相続人がいない・放棄した場合のみ、相続財産管理人の申し立てができます。
放棄後の注意点
-
親族など第三者が遺品を勝手に処分すると、無効となるリスク
-
通帳の引き出しや家の片付けも「単純承認」と判断される場合がある
-
不動産や土地の管理義務は放棄後も一定期間課される
このような管理義務や手続き上のリスクにも注意が必要です。
特殊相続ケースの取り扱い―再転相続や遺言が絡む場合の全員での放棄への影響
全員での相続放棄にも、特殊な相続ケースが影響を及ぼすことがあります。特に再転相続や遺言がある場合には下記のような注意が必要です。
-
再転相続
先順位の相続人が放棄したことで、次順位の相続人に相続権が移り、その人がさらに放棄することを「再転相続」と呼びます。この場合も3か月の期限が開始するタイミングが異なるため、各関係者の状況確認が重要です。
-
遺言がある場合
遺言書により特定の人に財産が遺贈されていても、法定相続人が放棄すれば遺贈の効力や財産の移転方法が複雑化します。遺言による指定分と法定相続分の調整が必要になるケースも見受けられます。
-
不動産や土地が絡む場合
相続放棄後も不動産の管理義務が残ることや、固定資産税の納税義務が問われる例も少なくありません。相続財産管理人選任後は、この管理人がこれらの清算業務を担います。
複雑なケースでは、専門家への相談や追加の書類手続きにより、リスクの最小化がはかれます。各ケースごとに正確な判断が求められるため、早めに情報収集と相談を進めてください。
全員で相続放棄した場合の借金・不動産・相続財産の帰属と処理法
負債の法的処理と保証債務の注意点―債権者や保証人に関する留意点
全員で相続放棄をすると、相続人は被相続人の借金や保証債務の返済義務を一切負いません。相続放棄が成立した時点で、債権者は放棄した相続人に対して請求できなくなります。兄弟姉妹全員が放棄した場合も同様です。ただし、次の順位の相続人が生じるため、その人が放棄しない限り債権者への請求権は移ります。
また、被相続人が連帯保証人だった場合、その保証債務も一緒に放棄できます。しかし、生前に保証していた第三者がいた場合は新たな保証人にはなりませんが、全相続人の放棄が成立するまでは慎重に手続きを行う必要があります。
負債に関する注意点の比較表
| 項目 | 相続放棄しない場合 | 全員相続放棄した場合 |
|---|---|---|
| 借金の返済責任 | 発生 | 発生しない |
| 保証債務 | 引き継ぐ | 引き継がない |
| 債権者の請求先 | 法定相続人 | 次順位相続人または管理人 |
不動産・土地の管理と所有権の推移―空き家・土地・資産の実務と負担を解説
全員で相続放棄した場合、土地や建物、家屋などの不動産は相続財産として誰のものにもなりません。所有権の推移としては、次順位の相続人へ権利が移り、全員が放棄すると最終的には国庫へ帰属します。それまでの間、不動産の管理義務は相続人が現に占有している場合のみ一時的に課されます。
具体的な注意点として、放棄後は相続人が家や土地など不動産を勝手に使用したり、売却・処分したりすることはできません。賃貸物件が含まれる場合や空き家状態の場合でも放棄後の管理や固定資産税などに注意し、必要に応じて早めに専門家へ相談することが推奨されます。
主な負担・手続きの比較リスト
-
不動産の勝手な処分は認められない
-
占有している場合のみ最低限の管理義務
-
全員放棄後は「相続財産管理人」による管理へ移行
-
土地や家屋の維持費用が発生する場合は負担が続く場合あり
相続財産管理人の役割と選任の全手続き―家庭裁判所への申立てと手続き流れ
全員で相続放棄が行われると相続人がいなくなり、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てを行います。管理人は遺産の整理や清算、国への帰属手続きまでを請け負う専門職(多くは弁護士や司法書士)です。
相続財産管理人選任までの流れ
- 全員が相続放棄の申述を完了(家庭裁判所で受理)
- 利害関係者(多くは債権者や管理会社、自治体)が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て
- 必要な書類(除籍謄本・戸籍謄本など)を提出し、裁判所の選任決定を待つ
- 管理人が選任されると遺産の点検・清算作業が始まり、借金返済や不動産処理を進める
費用の目安や管理人の主要業務
| 内容 | 概要 |
|---|---|
| 申立て費用 | 数万円〜十数万円(管理人報酬・予納金を含む) |
| 必要書類 | 戸籍謄本・除籍謄本・遺産目録等 |
| 主な業務内容 | 財産の調査・解約手続き・残余財産の国庫帰属の手続き |
全員で相続放棄する場合、それぞれのリスクや費用、相続財産管理人に関する知識を正確に押さえておくことで、余計なトラブルを回避しやすくなります。相続放棄後の家の片付けや管理、税金問題など、最終的には専門家への早めの相談が推奨されます。
相続放棄を全員でする場合の申述手続き完全マニュアル:書類・費用・申請の流れ
相続放棄を全員でする場合には、手続きの流れや必要な書類、費用、そして申述後の流れまで正しく理解しておくことが重要です。兄弟姉妹や相続人が複数いるケース、借金や土地などの資産・不動産が関係するケースでも、共通の注意点があります。ここでは、効率的な申述準備から受理完了までのステップごとに解説します。
書類の準備から申述書作成のポイント―効率的な必要書類のまとめ方
全員で相続放棄を行う場合、準備する書類を一つ一つ抜け漏れなく揃えることが円滑な手続きのコツとなります。強調したいポイントは以下です。
-
相続放棄申述書(各相続人ごとに必要)
-
被相続人の住民票除票や戸籍謄本
-
相続人全員の戸籍謄本, 住民票
-
家庭裁判所への宛名・封筒, 切手
-
その他の関係書類(不動産登記簿謄本・遺言書の写しなど、必要に応じて)
どの書類がどの相続人にも必要かを明確にしておけば、まとめて取り寄せ作業も簡便化できます。
| 必要書類 | 取得先 | ポイント |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所 | 各自が署名押印 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 市区町村 | 死亡の連続した戸籍まで全て |
| 相続人の戸籍謄本 | 市区町村 | 各相続人について |
| 住民票 | 市区町村 | 場合により不要の場合も |
申述書は家庭裁判所にて様式が案内されており、正確な記載が求められます。家族でまとめて行う場合でも、一括提出ができるため効率的に進められます。
申述費用の内訳と負担削減術―依頼先別の費用比較とコツ
手続きには費用がかかりますが、全員でまとめて申請することでコスト削減も可能です。主な費用の内訳は以下のとおりです。
-
裁判所へ申述する際の収入印紙(1人800円)
-
郵便切手や書類取得の諸経費(1人1,000~2,000円目安)
専門家に依頼した場合の費用感は以下の表を参考にしてください。
| 依頼先 | 手続き費用(1人あたり) | 特徴 |
|---|---|---|
| 自力申請 | 約1,800~3,000円 | 必要書類取得や記載に注意 |
| 司法書士 | 10,000~30,000円前後 | 書類収集・申請代行・相談込み |
| 弁護士 | 30,000~60,000円前後 | 複雑な争いがある場合や債務整理対応 |
兄弟や家族でまとめて依頼・提出することで書類収集や相談料の割引が期待できる場合があります。複数人同時申述には対応している事務所を選ぶのがポイントです。
申述後の裁判所対応:照会書への回答と受理通知―不備防止と申述完了までの注意点
申述が受理されると、家庭裁判所から照会書が各相続人に郵送されます。照会書には正確に回答し、求められる書類や追加情報も期日までに送付しましょう。
-
期日遵守・内容確認:記載ミスや添付書類の漏れは不受理の原因となるため、再度案内内容をよく確認してください。
-
受理通知:照会書の回答後、問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、これで手続きが完了します。
【注意したいポイント】
-
書類の内容や回答の不備があると家庭裁判所から再提出を求められる場合があります。
-
全員が放棄した場合、その後は次順位の相続人や相続財産管理人の選任など二次的対応が必要になる場合があります。
円滑な手続きのためにも、事前準備と確認は必須です。全員での相続放棄時は特に書類の共有と進捗管理をしましょう。
管理義務の詳細と放棄後も続く責任の実態
法律で定める管理義務の範囲と期間―財産維持義務や損失防止責任の具体例
相続放棄をした場合でも、すぐにすべての責任から解放されるわけではありません。法律では、次の相続人や相続財産管理人が決定するまでの間、財産の現状維持や損失防止のための管理義務が定められています。この管理義務は、放棄した相続人が「現に占有している財産」に限り発生します。
例えば、被相続人名義の不動産や預金、現金などを自宅で保管している場合、それを適切に保存し、勝手に使用したり処分しないことが求められます。管理義務の期間については、相続財産管理人の選任が完了し財産を引き渡すまで続きます。不動産の賃貸契約や共有資産などが含まれる場合には、損害防止や清掃、適正な保管が必要です。
主な管理義務の範囲と期間
| 管理対象 | 義務内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 不動産 | 建物・土地の現状維持、施錠など | 管理人に引渡すまで |
| 預金・現金 | 無断での引き出し・使用の禁止 | 管理人に引渡すまで |
| 貴重品・証券類 | 紛失・損壊防止のための安全保管 | 管理人に引渡すまで |
このように、相続放棄後も財産管理の責任はしばらく続くため、正しい方法で対応しないと後から責任を問われることがあります。
不動産など具体財産の管理実践例―現状維持や責任範囲について詳しく
不動産などの財産を管理する実際の場面では、次のような措置が必要です。
-
建物のドアや窓の施錠、雨漏りの点検
-
庭の手入れやゴミの撤去で火災などのリスク回避
-
賃貸中であれば家賃を維持し、勝手に契約を解除しない
-
土地の場合は無断転用させないよう柵の設置や定期巡回
-
遺品や貴重品も勝手な処分や廃棄はせず、安全な場所で保管
管理義務の対象となっている間に財産を処分したり勝手に使用すると、相続放棄の効力を失う可能性があり法的責任が生じます。放棄後は、財産の管理について第三者や専門家に相談し、できる限り客観的に証拠や記録を残しておくことも重要です。
管理実践のポイント
-
施錠や点検で現状維持
-
権利移転まで個人的利用や処分は絶対にしない
-
弁護士や管理人と連携して記録を保管
きちんと管理を行うことで、後々のトラブルや責任追及を回避できます。
管理義務違反時の法的制裁や救済措置―過去の裁判例やペナルティの紹介
管理義務を怠った場合、裁判所や他の利害関係人から責任を問われることがあります。実際に、相続放棄後に現金や家財などを私的に処分したケースでは、「相続財産の消費」とみなされ、放棄の効力が否定されるなど法的制裁が科されました。
違反例と主な制裁内容
| 違反内容 | 制裁・法的措置 |
|---|---|
| 現金・貴重品の流用 | 相続放棄の効力喪失、損害賠償請求 |
| 不動産の勝手な賃貸 | 賃借契約の無効化、損害賠償請求 |
| 家財・遺品の売却 | 売却益の返還請求、悪質な場合は刑事責任 |
管理義務違反が明らかになった場合、他の相続人や相続財産管理人、債権者から損害賠償を請求されるリスクもあります。一方で万が一、やむを得ず財産の一部を処分しなければならなかった場合には、その経緯や理由を残しておき、専門家へ速やかに相談することが救済のポイントとなります。
トラブル回避のためにも、相続放棄後の財産管理はルールに従い厳密に遂行することが求められます。
相続財産管理人の選任実務と費用負担の現実
選任申立ての具体的手順と必要書類―家庭裁判所での実務的対応策
相続人全員が相続放棄を行うと、不動産や借金など相続財産が残った状態となり、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てが必要です。申立ての際は、以下のステップを順番に進めます。
- 必要書類の準備
-
被相続人の住民票除票・戸籍謄本
-
全相続人の戸籍謄本(除籍含む)
-
相続放棄申述受理証明書
-
被相続人の遺産目録
-
財政状況報告書
-
不動産登記事項証明書や預貯金残高証明など
- 管轄家庭裁判所への申立て
- 原則、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てを行います。
- 申立書・手数料納付
-
申立書の作成(フォーマットは家庭裁判所で入手可)
-
収入印紙・郵便切手の用意が必要です
ポイント
全員放棄の場合、関係書類が増えるため、一つ一つの書類を確実にそろえましょう。
特に遺産目録や不動産関連書類の不備はトラブルにつながります。
申立てから選任までは2~3か月ほどかかるケースが多いのが実情です。
管理人の報酬体系と予納金の支払い負担―負担軽減策や予納金が払えない場合の対応
相続財産管理人の報酬や費用には明確な基準があります。主な負担は「予納金」と「管理人報酬」です。予納金は申立人が家庭裁判所に納める費用で、多くの場合20~80万円が相場となります。管理人が資産の換金や負債整理をするため、この予納金から報酬や実費が支払われます。
下記は費用の目安を示す表です。
| 項目 | 費用の目安 | 説明 |
|---|---|---|
| 予納金 | 20万~80万円 | 財産規模で変動 |
| 申立手数料 | 数千円 | 収入印紙代等 |
| 書類取得費 | 1万~2万円 | 戸籍等の発行費 |
負担軽減策としては、不動産や預貯金が残っている場合は換価処分により相続財産から費用が支払える場合があります。しかし、資産が少ない、もしくは予納金が支払えない場合は、裁判所に減額や分割を相談できる場合もあります。
ポイント
-
予納金準備が困難な場合、法テラスなどの利用も検討できます。
-
複数の相続人がいる場合、費用分担や代表者による一括負担も可能です。
管理人不在時のリスクと対応策―未選任時の問題と法的対策
相続財産管理人が未選任のままでいると、遺産が放置され複数のリスクが発生します。代表的な問題点は以下の通りです。
-
不動産の管理・処分ができず、税金(固定資産税)の請求が続く
-
借金や未払い債務の督促が相続人へ届く可能性
-
空き家や土地が放置され、近隣や市区町村から苦情や行政指導
リスクへの対応策としては、次の行動が有効です。
-
管理人選任までの間、最低限の管理義務(ゴミ処理や閉め忘れ確認など)を果たす
-
自治体への状況説明と連絡体制の構築
-
遺産放棄後の「処分権限」には制限があるため、勝手な売却や占有は控える
適切な手続きをせず放置すると、法的な責任が問われる場合もあるため注意が必要です。相続放棄後も管理義務が残る財産があるときは、速やかに管理人選任を進めることが、安全かつ円滑な相続トラブル防止につながります。
相続放棄を全員で行った後に起こりうるトラブルと無効・取消しケースの実態
放棄無効となる典型例と申述不備―裁判所で却下されるパターン解説
相続放棄を全員で実施する場合でも、家庭裁判所が認めなければ無効となります。特に多いのが、必要書類の提出漏れや内容の不一致です。例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や全相続人の戸籍、申述書の記載事項が不十分な場合、放棄が却下される可能性が高まります。
さらに、放棄申述の期限(死亡を知ってから3ヶ月以内)を過ぎての申立てや、すでに遺産の処分を進めてしまった場合も無効の対象です。相続放棄後に借金の返済や財産の管理・処分を積極的に行ってしまうと「単純承認」とみなされ、放棄が認められなくなります。
代表的な却下理由と注意点は、次の通りです。
| 無効になる理由 | 注意点 |
|---|---|
| 申述期限の経過 | 死亡を知った日から3ヶ月以内 |
| 必要書類の不備 | 戸籍・住民票・申述書・財産目録 |
| 財産処分や借金返済 | 遺品整理や支払いなどに手を付けない |
このようなトラブルを防ぐためには、手続き前の書類確認と専門家への相談が重要です。
放棄後の相続手続き上の落とし穴―借金取立てや財産管理トラブルのケース紹介
全員が相続放棄した場合、よくあるトラブルが管理義務や債権者対応です。放棄を終えても、まだ不動産や家財が残っていれば「現に占有している者」は必要最小限の管理を続ける責任があります。たとえば、空き家や土地の放置で近隣トラブルや修繕費が発生するケースが少なくありません。
また、全相続人が放棄すると「相続財産管理人」の選任申立てが必要になる場合があります。管理人選任にかかる費用(予納金)は財産状況や家庭裁判所によって異なりますが、一般的には数十万円単位になることが多いです。
借金が残っていた場合でも、すべての相続人が放棄すれば原則としてその債務は引き継がれません。ただし、取立てや督促が来る場合は速やかに放棄を証明し、必要に応じて管理人の選任手続きに移行することが大切です。
主なトラブル事例
-
空き家や土地の放置による固定資産税の督促
-
借金の債権者からの取立て対応困難
-
管理人選任のための予納金や手続きの煩雑さ
これらの状況では、専門家へ早期の相談が望まれます。
取り消しや限定承認を検討すべき局面―法的手続きや再対応が必要な場合
相続放棄をした後に新たな財産や借金が判明した場合、特定の事情があると放棄申述の取消しや限定承認が認められるケースもごく一部存在します。ただし、「脅迫や詐欺」が原因で放棄した場合などごく例外的です。
もし遺産の全容がつかめない段階で放棄を検討しているなら、限定承認(相続財産の範囲内でのみ借金を支払う方法)が有効な場合があります。限定承認は全相続人で相談してから決断する必要があり、放棄との並行申立てはできません。
再度の対応が必要となる代表的な局面
- 放棄後に遺品整理で高額資産や新たな負債が発覚した
- 放棄意思が同意もなく第三者により申述された場合
- 成年後見制度の利用者など意思能力に疑義が残る場合
相続放棄や限定承認の手続きは、誤った対応で損害が生じるリスクがあるため、法的な知識や実務実績のある専門家への相談が不可欠です。全員による相続放棄はメリットだけでなく、細かな手続きや予期しないトラブルがつきものです。早めに全体像をつかみ、必要なステップを一つずつ進めることが安全な解決に繋がります。
兄弟姉妹・親族全員で相続放棄を進めるときの連携術
連名申請の効率化ポイントと必要書類―委任状や共通書類の適切な進め方
兄弟姉妹や親族全員で相続放棄を進める際は、事前の連携が手続きのスムーズさを左右します。相続放棄の申述は、各人ごとに家庭裁判所へ行いますが、以下の方法で作業負担を軽減できます。
効率化のポイント
-
戸籍謄本や除籍謄本、被相続人の住民票除票など、共通で利用できる書類は代表者がまとめて取得
-
委任状を活用し、1人が書類収集や提出を担当することで時間と費用の無駄を省く
-
同じ裁判所に同時に申し立てれば、相続財産管理人の選任など後の流れも円滑
相続放棄に必要な主な書類一覧
| 書類名 | 詳細・注意点 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 各相続人ごとに1通必要 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 死亡の記載があるもの |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 法定相続人の範囲を特定するため |
| 住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最終住所を証明 |
| 委任状 | 書類取得などの代理人を定める場合 |
兄弟のみの場合も、委任状を用いてまとめて申請することが可能です。行政書士・司法書士などに依頼する場合もこの流れを利用します。
親族間の合意形成で注意すべき点―意思決定やトラブル防止の実践例
相続放棄を全員で円滑に進めるには、初期段階での合意形成が非常に重要です。未確定なまま個々で手続きを進めると、相続順位が意図せず移行し、親族間に予期せぬ負担やトラブルが発生する恐れがあります。
注意すべきポイント
-
事前に放棄希望者同士で理由やメリット・デメリットを確認し、必要な情報を全員で共有する
-
意思決定は「全員一致」を原則とし、1人だけ放棄しない場合の影響も説明する
-
負債の有無や不動産(特に土地)・遺品の取扱い方針を協議し、担当者が進行管理する
実践例
-
放棄後の不動産管理義務や税金(固定資産税)が発生し続けないよう、あらかじめ全員放棄後の流れを専門家に確認
-
借金返済が発覚した場合も負担者が出ないよう、全員で相続財産管理人選任を申し立てる
合意書類やLINEグループ、メールなどで協議内容を記録しておくと後のトラブル防止に役立ちます。
申立て時の代理人利用のメリットと注意点―代理申請における実務上のポイント
相続放棄の申立てで代理人を立てる場合、司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼することで申請の正確性や効率が向上します。
代理人利用のメリット
-
書類の不備や要件ミスを防ぎ、迅速に申立てを完了できる
-
複雑な場合や遠方在住でも、本人の手間を大幅に削減
-
必要書類の案内や管理義務へのアドバイスも受けられる
注意点
-
代理申請には必ず委任状が必要。相続人ごとに署名・押印しなければなりません
-
費用は司法書士や弁護士ごとに異なり、申請人数や地域によっても変動
-
代理申請後も家庭裁判所から各相続人へ本人確認の連絡が入る場合があるため、必ず連絡が取れる状態にしておくことが重要
適切な代理人選びにより、「申請時の煩雑さ」「書類再提出のリスク」などを低減し、安心して手続きを進められます。
上記ポイントを押さえて全員で連携することで、相続放棄はよりスムーズかつ安全に完了できます。
実例で学ぶ!相続放棄を全員で行った場合のケーススタディ集
借金がある家族での全員放棄事例―負債回避や手続きの詳細を実例で解説
借金を抱えた家族の場合、相続人全員で相続放棄を行うケースが増えています。例えば、被相続人に数百万円規模の消費者ローンやクレジット負債があった場合、兄弟や親族全員が相続放棄の手続きを選択することは一般的です。相続放棄の申述は各人が家庭裁判所へ個別に行いますが、同時期に書類を提出し全員放棄が成立すれば、負債は請求されません。主な手続きの流れとしては、死亡届提出後3か月以内に相続放棄の申述書と戸籍など必要書類を準備し、家庭裁判所への提出を行います。
費用や必要書類は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述書類 | 放棄申述書、被相続人の除籍謄本、申述人の戸籍謄本等 |
| 手続費用 | 1人あたり約1万円〜3万円(専門家に依頼した場合) |
| 期間 | 申請後1ヶ月前後で受理 |
相続放棄を全員で行う場合、借金の取り立てリスクを回避できますが、手続きの抜け漏れに要注意です。
不動産を含む相続放棄の成功・失敗例―管理義務や所有権移動のリアル
相続財産に不動産が含まれる場合、複数の兄弟姉妹全員が相続放棄を選択する事例も増えています。成功例では、遺産に古い空き家や管理困難な土地が含まれていたケースで全員放棄を選択した結果、不要な固定資産税の負担から解放され、管理義務からも早期に抜け出せました。一方、事前に家屋の片付けや売却を行った場合には注意が必要です。すでに不動産を処分・管理した行為が「単純承認」とみなされ、相続放棄自体が認められない失敗例も発生しています。
全員放棄時の主要ポイントを整理しました。
| 状況 | 成功のポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 全員で不動産放棄 | 物件の占有・管理をせずに手続き | 先に遺品整理や草刈りをすると放棄不成立のリスク |
| 固定資産税 | 放棄後は相続人に課税されない | 放棄完了まで一時的に課税される場合あり |
土地や家屋が関係する放棄には、「何も手を付けない」ことが重要です。
専門家が介入して解決した複雑事例―法的な調整や複雑ケースの実践紹介
実際に兄弟のうち1人だけ海外在住だったり、相続順位や遠縁の甥姪まで放棄が及ぶ複雑なケースでは、司法書士や弁護士が介入したことで円滑な手続きが進んだ例があります。例えば、全員放棄後に家庭裁判所へ「相続財産管理人」選任申立てを行い、管理人が不動産の売却や残債の清算、残余財産の国庫帰属まで一括対応しました。
専門家へ依頼するメリットは以下のリストで整理できます。
-
複雑な戸籍や書類調査、裁判所とのやり取りも安心
-
管理義務や法律的ミスを未然に防げる
-
遺産のプラス・マイナスの調査も依頼できる
難易度が高い複雑案件ほど経験豊富な専門家のサポートは不可欠です。信頼できる専門家に早めに相談することで、安心安全な相続放棄が実現できます。